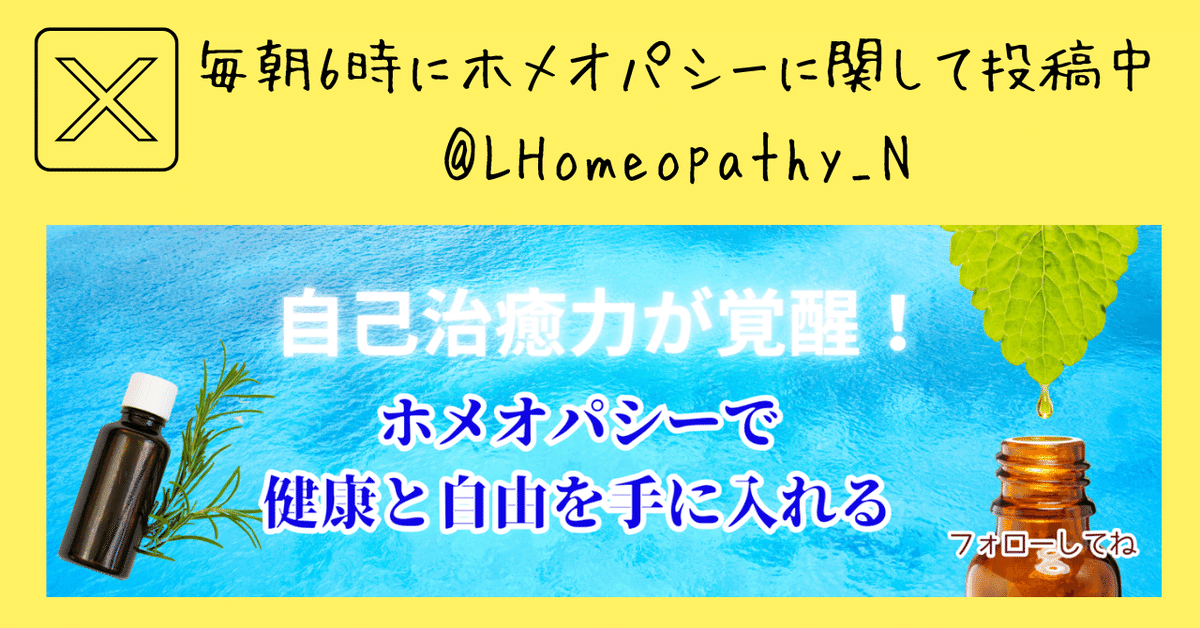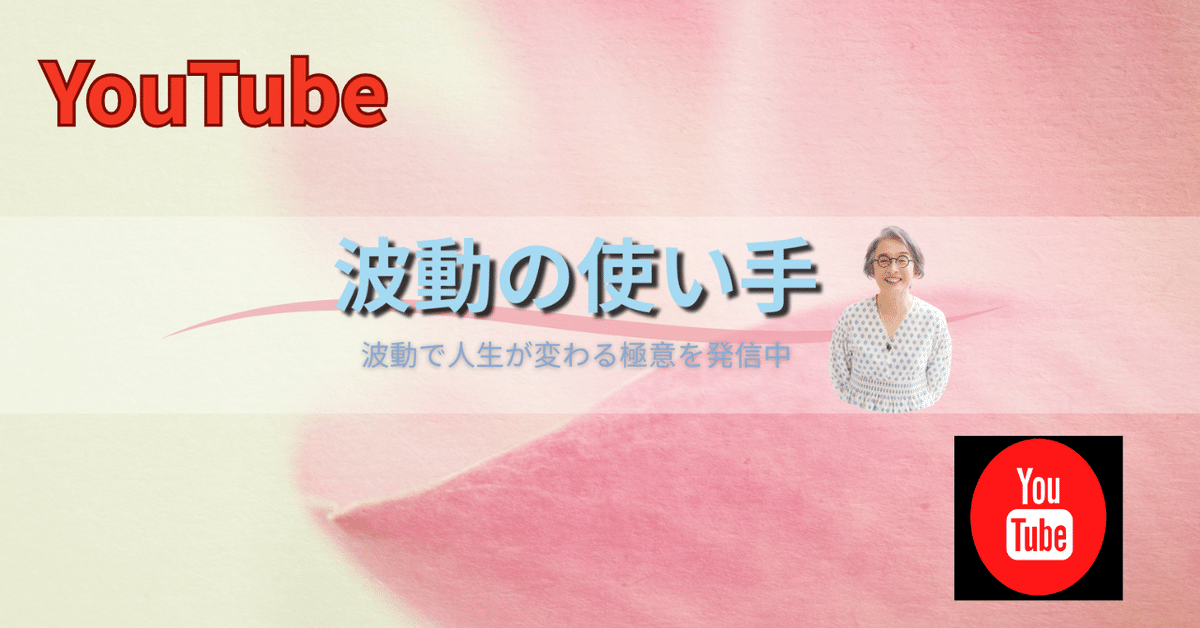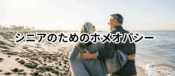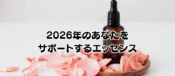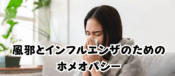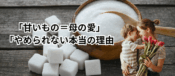砂糖中毒とインナーチャイルド〜甘いもの=母という方程式

薬や病院に頼らず自己治癒力を上げて健康に生きる方法を伝えている、波動療法家・ホメオパスの金澤千佳です
今や「砂糖は健康の敵」というのは常識になりつつあります。糖質制限、ローカーボ、ケトジェニックなど、どんな立場の栄養学や食事法でも共通しているのが「砂糖を摂るな!」というメッセージです。
しかし、多くの人がこの事実を知りながらも、砂糖をやめられません。むしろドラッグよりも中毒性が高いとさえ言われる砂糖。なぜ、私たちはこれほどまでに砂糖に依存してしまうのでしょうか。
その答えは、意外にも「母子関係」にありました。
砂糖の原材料「サトウキビ」とホメオパシー

砂糖のもとである「サトウキビ」は、ホメオパシーにおいてレメディとして使用されています。このレメディの中心的なテーマは**「自己愛の欠如」**です。
ホメオパシーの観点から見ると、サトウキビのレメディは母子関係に深く関連しており、特に以下のような心理的背景を持つとされています。
自己愛の欠如の根源
当然受けるべき母親からの愛情を受けられない恐怖。そこから生まれる「母親に見捨てられる」という思い込み。これが「自己愛の欠如」の中心にあると考えられています。
その結果、愛情や注意を求めることに絶望的になり、代わりに「甘いもの」でその欠乏感を埋めようとするのです。
砂糖中毒から抜け出せない心理的要因

多くの人が無意識に抱えている、砂糖への依存を生み出す心理的要因をまとめました。
5つの心理的要因
-
抱きしめて欲しい気持ち
満たされない愛情欲求が、甘いものへの渇望として現れます。 -
不足感による爪噛み、指しゃぶり
幼少期の口唇期の欲求不満が、大人になっても無意識の行動として残ります。 -
食べずにはいられない衝動
心の空虚感を、食べ物で埋めようとする代償行為です。 -
両親から愛されなかったという「妄想」
実際に愛されていたとしても、そう感じられない心理状態があります。 -
究極の想い:私の人生で愛が不足しているという感覚
これが最も根深い要因です。母子関係由来のこの想いが、砂糖への依存を生み出し続けます。
サトウキビレメディによく見られる症状
ホメオパシーにおけるサトウキビレメディが必要とされる人には、以下のような特徴的な症状が見られます。
身体的症状
- 食べた直後にもう胃が空っぽのように感じて、飢えたような食欲を覚える
- 一般的に虚弱体質
- 間食を食べたがる
- 決まった食事の時間に食事を摂らないと疲労やめまいを感じる
- 甘いものへの強い欲求
- 消化器系統の問題
- 爪噛み、指しゃぶり
- 食べずにはいられない
- 乾燥肌
精神的症状
- 孤独感
- 落ち着きのなさ
- 不平、不満が多い
- 母親といると緊張する
- 嫉妬深い
- 注意を惹くためのおしゃべり
- 朝食前のイライラ
- 集中力がない
- 攻撃的になる
- 自分に対する不平、不満
- 抱きしめて欲しいという欲求
根本的な原因
これらの症状や心理状態を生み出す原因として、以下のようなものが考えられています。
- 感情的な拒絶を受けた経験
- 見捨てられた経験
- 母乳で育てられなかった
- ご褒美として甘いものをもらっていた
- 母親からの愛情不足(実際または感覚的な)
「甘いもの」は「母」そのもの
興味深いことに、サトウキビに似たレメディとして「チョコレート」も存在します。
つまり、ホメオパシーの世界では「甘いもの」そのものが「母」を象徴していると考えられているのです。
私たちが甘いものを求めるとき、実は無意識のうちに母親の愛情、温もり、安心感を求めているのかもしれません。
おわりに
砂糖中毒は、単なる味覚や生理的な依存だけでなく、深い心理的な背景を持っています。
「甘いものがやめられない」という現象の背後には、満たされない愛情欲求や自己愛の欠如といった、幼少期の母子関係に由来する深い心の傷が隠れている可能性があります。
もし、あなたが砂糖への強い依存を感じているなら、それは単なる意志の弱さではなく、心が何かを訴えているサインかもしれません。
自分の心と向き合い、本当に必要としているものは何なのか、見つめ直してみることが、砂糖中毒からの脱却への第一歩となるでしょう。