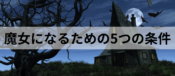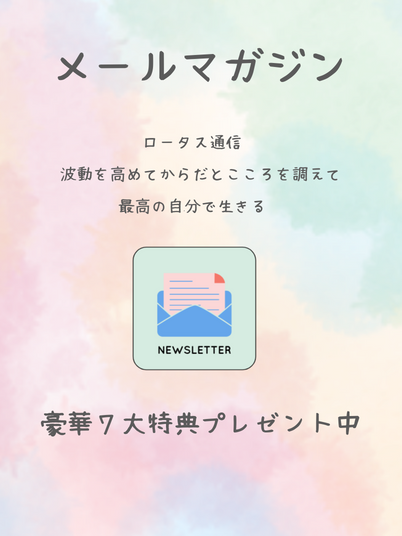ホメオパシーで急性疾患と慢性疾患に対応する上での基本はこれだ!

自然治癒力を高めることで健康不安を取り除き、自由と時間を手に入れることができる
ホメオパス(自然療法家)の金澤ちかです
梅雨に入り、湿気と気温の変化に体調を崩しやすい時期ですね
そんな時こそ、ホメオパシーの出番ですが、レメディーの選び方がOKだとして、次に問題になるのがポーテンシー(レメディの強さ、弱さの程度)の選び方と飲み方ですね
そして、それは慢性と急性ではやり方が異なります
今日は、その辺りを解説します
ホメオパシーで急性的な症状に対応する

症状は大きく分けて、「急性」と「慢性」があります
線引きは、どれくらい患っているか?になります

そういったものはもちろん急性ですが、
定義としては、ある症状が
続いて半年くらいまでなんですよ

一概に決めることは難しいので例外もありますが、基本的には、ある症状が続いている期間が半年以内のものを急性と呼んでいます
家庭でのセルフケアは、この「急性的症状・疾患」のみが対象です
ここだけは、お間違いのないように〜
慢性疾患・症状を自分で治そうなどと思ってはいけませんよ〜

30Cを使います

ヨーロッパやオーストラリアには自然食料品店やビタミンショップなどでも普通にレメディーが市販されていますが、通常ポーテンシーは30C以下です
ものによって30Cより低いものが売られていますが、30Cより高いものつまり200Cは原則的には売られていません(例外もありますが)
それが、安全基準ですね
副作用がないからと言う話を信じて、高いポーテンシーのものをセルフケアとして飲んだりするのは海外では考えられないことなのです!
200年の歴史を持つ国際的な考え方を元にしたやり方の方が信頼性が高いと私は思っています

ある時は数分置きに、
ある時は1日4回くらい、
というようにその都度症状に応じて
考えなければなりません

基準は下記の通りになります
「服用量」
服用量は、症状の急性の度合いとレベルによって決まります。
突然の強い症状(乳幼児の急な高熱など)の場合は、10分から30分間隔が必要とされています。それより穏やかな症状の場合は、1時間から2時間置きで良いでしょう。
さらに、もっと穏やかな場合は、4時間から8時間置きが良いでしょう。
例:
- 高熱、食中毒、非常な痛み: 10分から30分ごと
- 旅行中の下痢など: 1時間から2時間ごと
- 進行の遅い風邪: 4時間ごと
前にも書いたように、安全だから大量に飲んでもいいと思うのは大きな勘違いです
大量に飲めば、少なくとも好転反応やプルービングが出る可能性は高くなります
そうなると、家庭では収拾がつかなくなることもあるのです
どうか、適量を心がけてください

飲んでもいいのかしら?
どれが効いたかもわからないし
好転反応が出やすくなります

そうは言っても、家庭で使う場合、一つのレメディーに絞りきれないことはよくあるのですね、ではそういうときにどうしたら良いのでしょうか?
一つずつ、時間を空けて摂ってくださいといつもお伝えしています
数種類を一度に口に入れるのではなく、注意深く様子を見ながら候補を時間を空けて摂っていくのが一番安全な方法です
空ける時間は、30分から1時間で構わないので、次からそういう風にトライしてみてくださいね!
ホメオパシーで慢性的症状に対応する

ホメオパシーで、慢性的な症状や、疾患、持病と呼ばれてるようなものに対応することは可能です
病院に掛かっていた人もしばらくは併用で様子を見ながら使うことをおすすめしますが、但しそれはセルフケアではなく、プロのホメオパスにかかるという前提でです
ホメオパシーで対応できる疾患はいろいろありますが、特に下記のようなものには向いています
- 子ども:不登校、ADD(ADHD)、ひきこもり、発達障害全般など
- 婦人科系の疾患:月経の異常、更年期障害、不妊症、PMS(生理前症候群)など
- 心の問題:不安神経症、パニック障害。うつ状態。PTSDなど
- アレルギー疾患:アトピー性皮膚炎、喘息、花粉症、鼻炎など
- そのほか:リウマチ、関節炎、胃腸障害、糖尿病、高血圧など
怪我の中でも骨折や、大出血を起こしているものは当たり前ですが、即、病院へ行ってくださいね
併用してレメディーを摂ることは構いませんが…
例えば、骨折などした場合にレメディーも併用すると骨の回復力は使わない場合よりも数段上がりますのでそういった使い方が一番賢いやり方です
何かの病気で手術が必要な場合も、レメディーを使うことで身体へのメスや麻酔のダメージを減らしたり、精神的ダメージを和らげたりすることも可能なんですよ
慢性症状では、レメディーも高いポーテンシー(より薄まっている=より強い希釈のもの)を使うことが多く、回数は症状によって本当にいろいろです
一粒で様子を見ることも多いので、多く摂ることに慣れている人にはびっくりされますが、それがクラシカルのやり方ですし、200年以上その方法でたくさんの成果を上げているのでご安心くださいね
まとめ
薬にも医師の処方箋がいるものと、薬局などでいつでも買える市販薬と区別があるように、ホメオパシーにもセルフケアで使っていいものと、プロのホメオパスに委ねるべきものと別れていることを認識している人が日本には少ないようです
低いポーテンシー、例えば30Cなら誰でも買えるか?というとそれも違います
日本は買えたりするようですが、諸外国をみても、いくらポーテンシーが低くても一般の人間が買えるレメディーの種類には限りがあります
Nosodes(ノソッズ)と呼ばれる病原菌や病気の細胞などを使ったレメディーは、低いポーテンシーだとしても気をつける必要がありますし、毒性の強いものは逆に低すぎるポーテンシーが良くなかったりもします
日本はホメオパシーに関してはまだまだ後進国なので、十分気をつけてお使いくださいね
包丁が料理に便利でも、同時に凶器となり得る道具のように、使い方を間違えると良いことばかりでないのが優れた道具には多いものなのです
ホメオパシーの可能性は大きいからこそ大切に知識を持って安心安全にお使いください
ご案内

本気でこころもからだも自分で調える!
自分を大切にしたいあなたのための特別セッション
今なら、無料で個人カウンセリングが受けられます
なかなか、レメディーがうまくヒットしない時は、こちら↓↓↓の記事をぜひクリック!